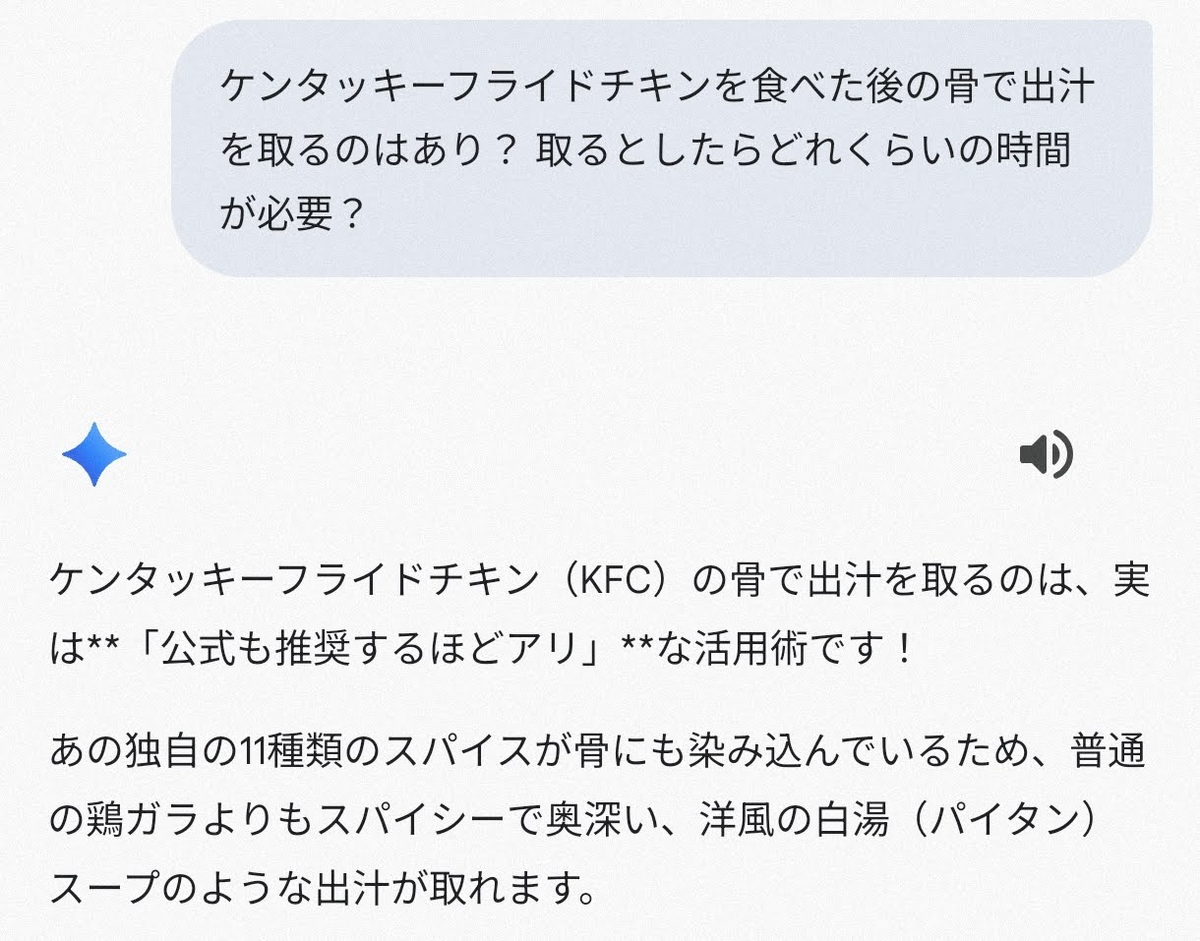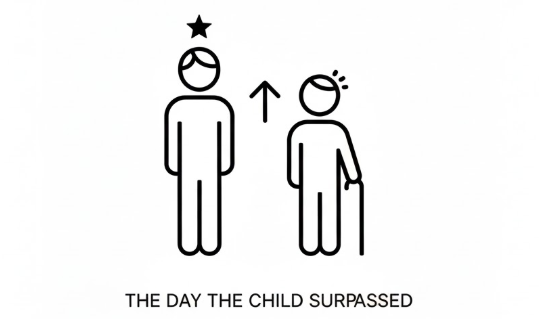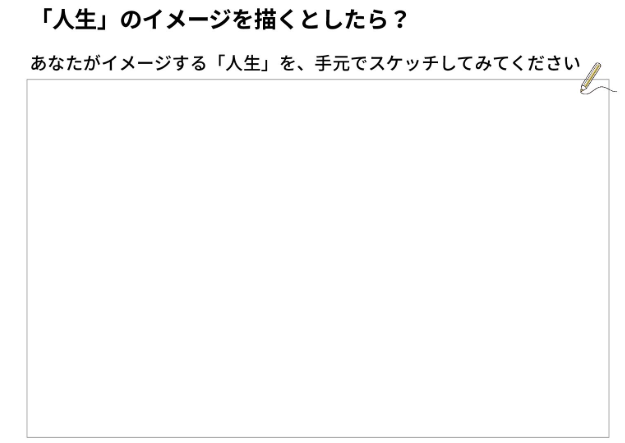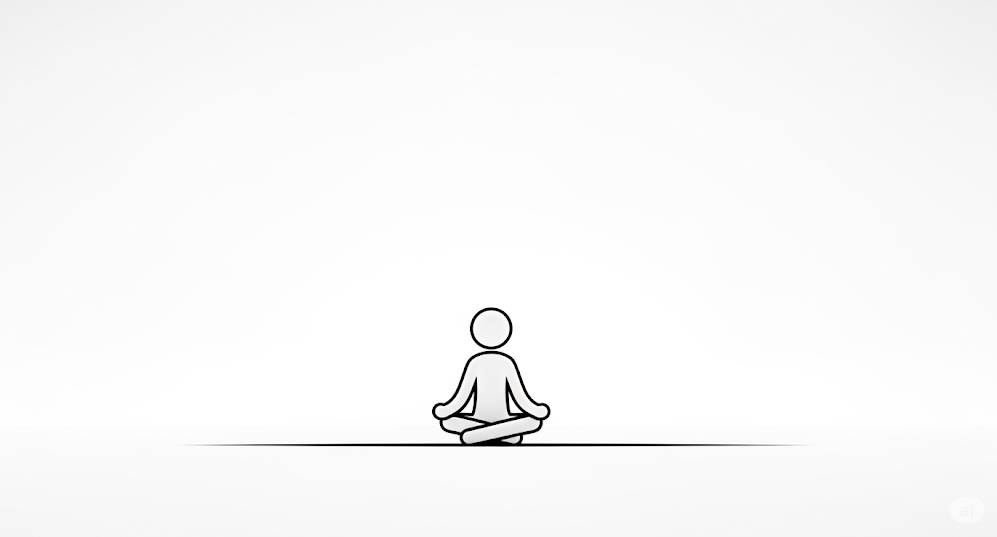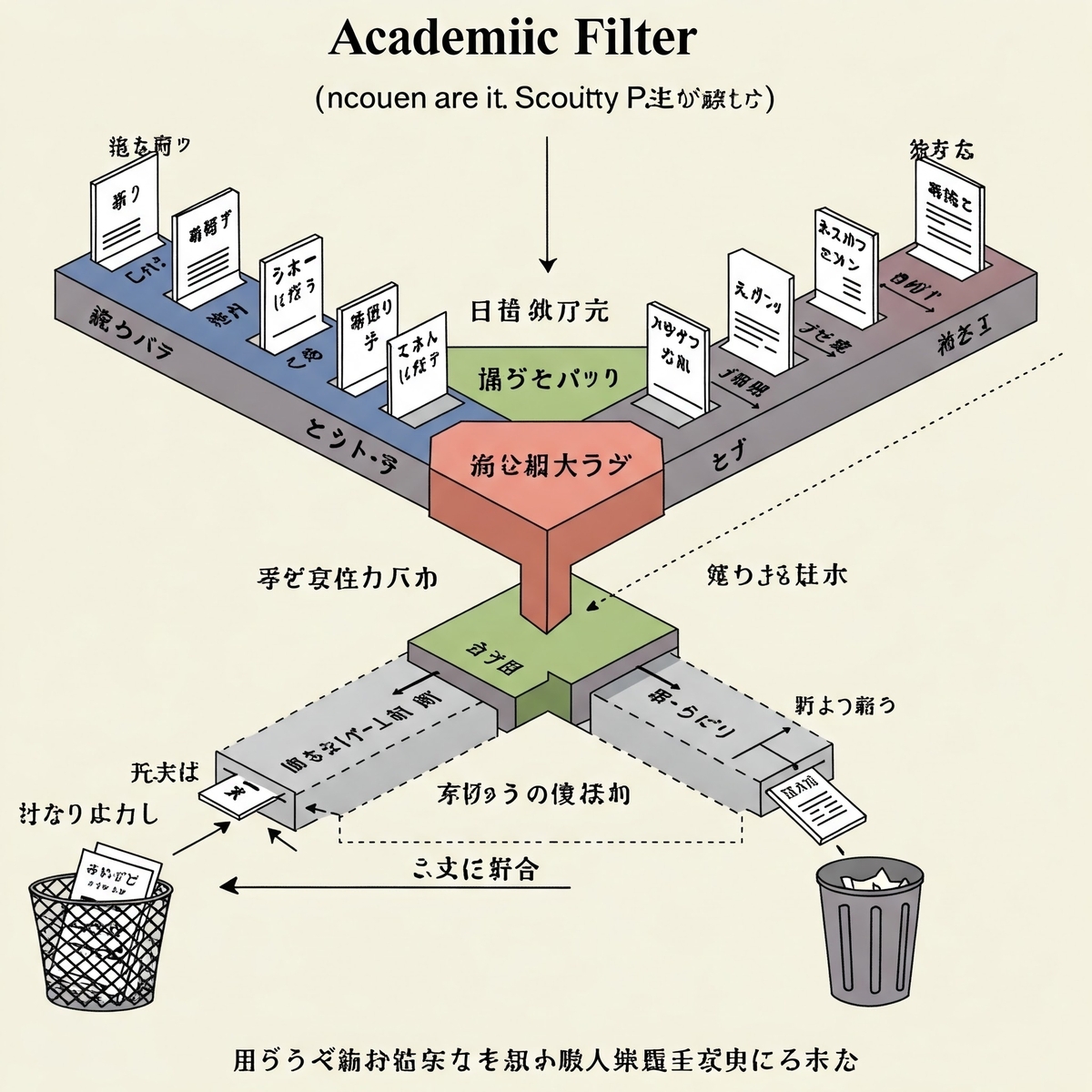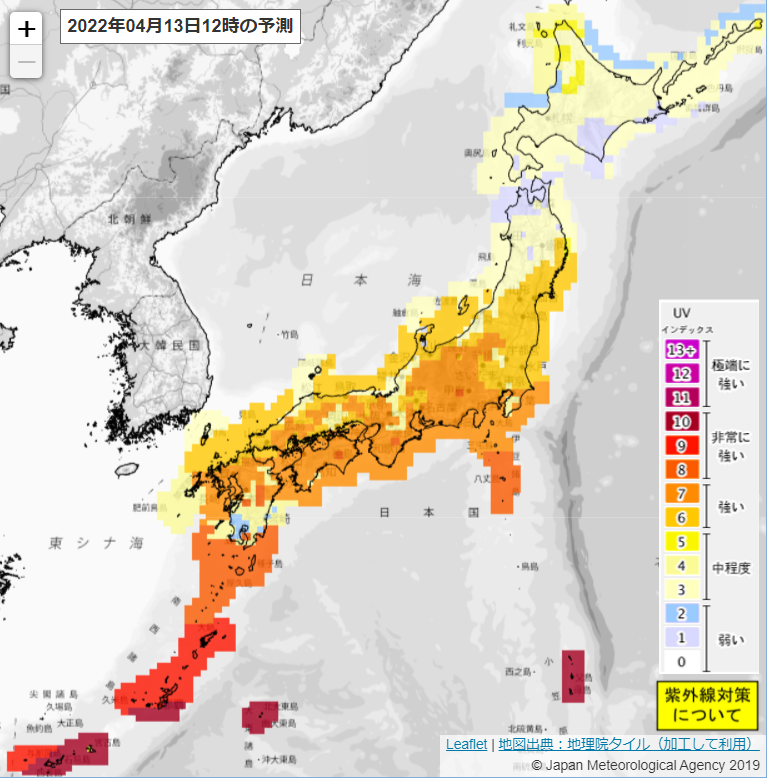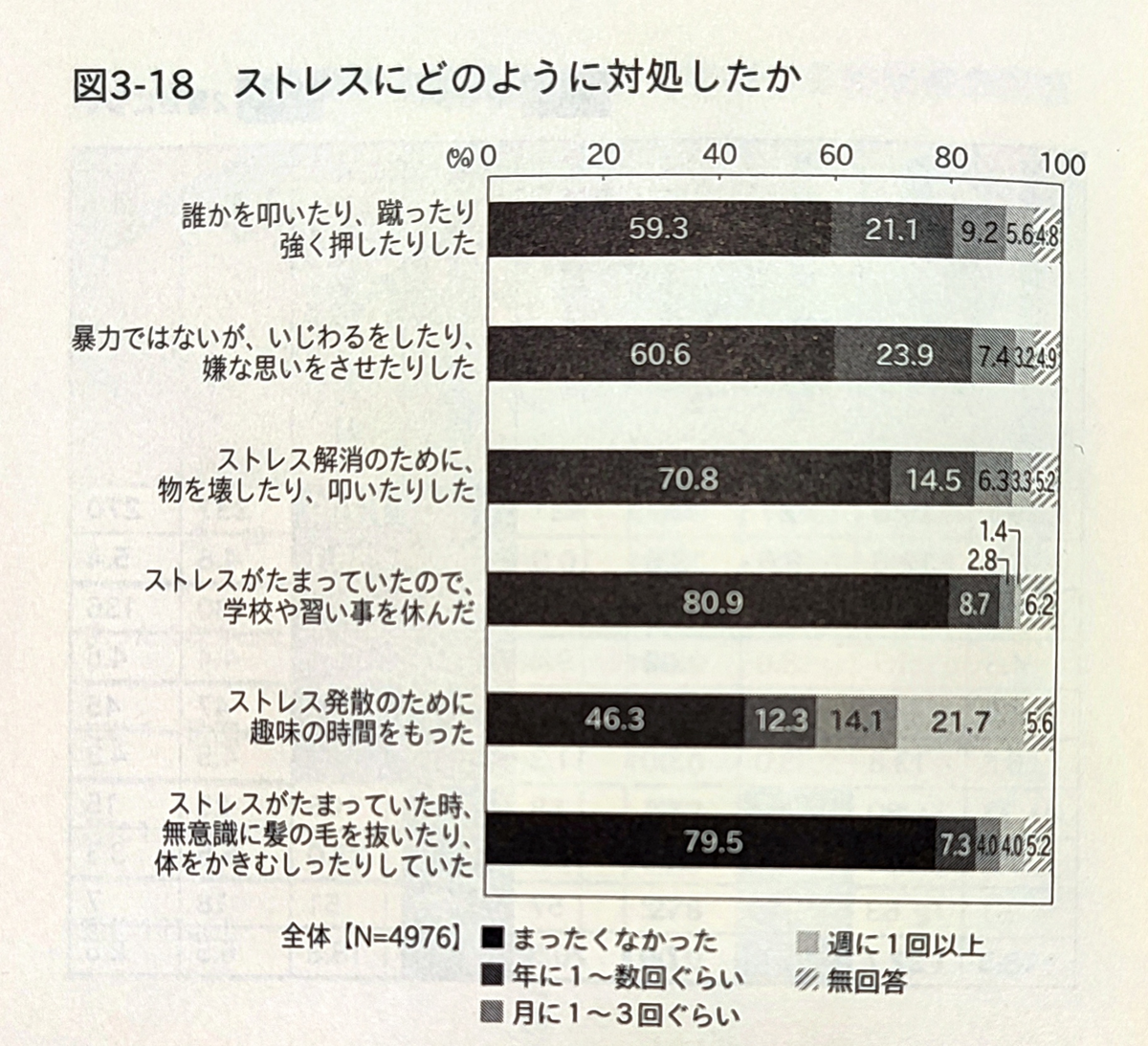先日、ようやく普通自動車の運転免許を取得しました。フルタイムで働きながら、子育てしながらなので、半年ぐらい掛かってしまいました。

※Geminiで生成した自動車教習所。それらしいが、かなりおかしい
この記事では、なぜ自動車の運転免許の取得をしようとしたのか、自動車教習所や運転免許センターでのあれやこれやを書いていきます。年齢が上がってから、免許を取得しようと考えている人の参考なると嬉しいです。
免許取得のきっかけ
大人のリスキリングとして、応用情報技術者試験やプロジェクトマネージャ試験に合格したのは以前に紹介した通りです。
プロジェクトマネージャ試験に20時間の独学で一発合格した方法 - 斗比主閲子の姑日記
次に何に手を出そうかと考えた時に思いついたのが自動車免許でした。
私は自動車というものにまったく興味がなく、パートナーが車好きだったので、自分で車の運転をする必要はこれまでの人生で一度もありませんでした。免許の取得率は高いといっても有資格者で8割ぐらいで、全員が取得しているわけでもないですしね。
ただ、友達と旅行をしたときに「レンタカーが使えたらもっと便利だったのに」と思ったり、車が必要なときはパートナーの予定の確認が必要だったり、車の運転ができないことで人生の選択肢が狭まっていると感じたことは、それなりにありました。
年を取ったら難易度が上がり、今だからこそ取れる資格で、取得することで人生の幅が広がるものを考えたとき、「自動車免許というのはかなりアリではないか?」と思い、免許を取ろうと決心したのでした。
教習所は合宿? 通学?
運転免許を取ると決めたら、次は教習所探しです。
どうやら世の中には一発試験という、運転免許試験場でいきなり免許を取れる人がいるとかいないとからしいんですが、私のようにまったく車を運転したことがない人間にはその選択肢はありません。
普通は自動車教習所に通うことになります。教習所でも、合宿形式と通学形式があり、どちらにしても、60時間程度の座学と実習が必要なようです。
合宿免許だとウィークリーマンションみたいなところに住みながら、ほぼ毎日教習を受けることで、1ヵ月も掛からず免許が取得できるみたいでしたが、さすがに仕事と家事育児をしているのに、長期間休みを取るというのはそう簡単ではありません。
60時間程度なら、週に4時間しか通えずとも、15週間、約4か月で取得が可能です。多少時間が掛かることは特に問題がないので、通学形式で教習所を選ぶことにしました。
Google mapのレビューで自動車教習所を決める
通う教習所はGoogle mapで調べることにしました。教習所の口コミサイトはあるにはあったんですが、ちょっと口コミ数が少なすぎるのと、この手のレビューをどこまで信用していいかが判断がつかず、普段からよく使っているGoogle mapのレビューなら、サクラかどうかも判断しやすいなと考えたからです。
教習所の料金自体は30~40万円ぐらいらしく、学生であればその金額の差は大きいでしょうが、私からすると多少お金を払ってもサービスが良い方が望ましいので、あまり料金は気にせず、レビューの点数が高い自動車教習所に入所することを決めました。
自動車教習所の入所手続きで、めちゃくちゃ違和感を覚える
入所手続きで自動車教習所の仕組みを聞いて、まず最初に思ったことは、「複雑すぎて、よく分かんない!」「説明が雑過ぎる!!」です。
特によく分からなかったのが、予約システムです。学科はWebで時間を決めて取れるのだけれど、技能(実際に車を運転する授業)が意味不明でした。「サイトをよく見てると空きが出ますから、予約してください」「キャンセルを教習所で待ってもらうのもいいですよ」「この学科を受けた後にこの技能を受けてください」とか、複雑すぎでした。
後は、教習所内も案内してもらうものの、「このスペースで自習してもらってもいいです」「学科はこの場所で、受講時には先生にこの紙を渡してください」「紙は受付で、受講前〇分に来てくれたら、お渡しできます」と、普通に説明してくれる内容が、全然頭に入ってきません。
いや、事実としてはその通りなんだろうけど、教習所がどういう仕組みで成立しているかの説明がなく、単に作業工程だけを教えてもらっているから、理屈が分からないと動けない私としては、覚えゲーをやらされているようで、非常に苦痛でした。
結局、通い始めてみたらなんとかこなせたんですが、とにかく言われた通りに動ける若者が来るところで、年を取ってから通い始めるのは難しい場所なんだろうなというのを、この時点で察しました。
学科はつまらない。技能は楽しいが、アドバイスが苦痛
入所手続きの後に30何万円を課金し、晴れて教習所に通うことになりました。
とりあえず簡単に終わるだろうと、学科をたくさん埋めて受講してみましたが、これが非常につまらなくて苦痛でした。教習所の先生と教習生の関係は、なぜか上下関係があり、さらに授業は双方向性がなく、しかも、授業の半分以上は動画が流されるだけです。昔の小学校の授業を思い出しました。
一度、教習所の先生に「これって、オンライン学習にしないんですか?」と聞いたら、「ここではまだ対応していないんですよ」とのことでした。後で調べたら、世の中には、学科をオンラインで提供しているところはちゃんとあるようなので、これは私の情報収集不足でした。
技能は、車という巨大なものをじわじわ自分の手足のように動かせるようになるのは、とても楽しかったです。正直不安が大きかったけれど、仮免を取るまでの教習所内を走る第一段階の12時間で、実際ほとんどの人が車の基本的な動作を覚えられるのだから、車の運転がそんなに難しいもののはずがないんですよね。
ただ、教習所の先生のアドバイスは、かなり苦痛でした。第一段階の12時間、第二段階の19時間の合計31時間と、後は、検定の時とかで、合計10人以上の先生に教えてもらいましたが、教え方が上手いと思ったのは3人ぐらいでした。
教え方が上から目線なのは論外だけれど、事前にその日学習する内容を説明されることはほとんどなかったし、「そんなやり方だと危ない!」「何を習ったの!?」みたいな、後から問題点をあげつらうようなことも結構されて、何度かかなり落ち込みました。
私も大人で、自分が人に物を教えることや、教え方を指導することもしてきましたから、「先生の教え方だと私には理解できないので、こういう言い方ややり方にしてもらえませんか?」と下手に出たりしたものの、基本的に解決されなかったため、「これはもう相性の問題と受け止めた方がいい」と思い、教習所にお願いして合わない先生と組まないようにしました。
教習所ビジネス自体が少子化で縮小する中で、恐らくは昔に比べたらこれでもマシになっているんでしょうけどね。運転を褒められると本当に気分が良く、やる気も出たので、「私もこれまで以上に人を褒めよう」と他山の石としました。
あ、技能だと、高速教習が楽しかったですね。ちょっとおっかなびっくりなところもありつつ、「とうとうここまで来たのかー」と自分の成長を実感できたので。
仮免前の効果測定をカンニング、長めのネイル、学科で寝る若者たち
教習所通いをしていて、技能で技術を習得する以外に、ちょっとした楽しみがありました。それは、私が普段の生活ではなかなか出会えない、20前後の若者の生態を垣間見れることです。
やはり、自動車教習所に通う人は若者が中心です。30代以上は感覚的に1割もいないように見えました。
服装はちょっと派手というかヤンチャな人が多い傾向はあって、タトゥーを入れてたり、ネイルが長い人がいたりして、「あー、若い人ってこんな感じなんだなぁ」と眺めていました。
結構驚いたのは、第一段階での仮免を受ける前の効果測定(学科試験的なやつ)で、堂々とカンニングする若者がいたことです。教習所の人が誰も見ていないからやっているのだろうけど、本番の学科試験はカンニングが出来ないのだし、なぜこの段階でカンニングをするのだろうと、非常に不思議に思いました。
後は、学科の授業でも若者は普通に寝てましたね。私みたいに年を取ると、いくらつまらない話でも右から左に聞き流しながら、寝るのは我慢できるわけですが、若者はそうじゃないですよね。先生に怒られているのを見て、「何だか高校時代に戻った気がする」と、タイムスリップした気分になっていました。
晴れて自動車教習所を卒業。運転免許試験場はハイテクだった!
悲喜こもごもあった自動車教習所も、卒業検定も難なく一発合格で、晴れて卒業となりました。
通っていた期間は半年弱で、正直行くのが憂鬱な時もありましたが、自分が確かな技能を獲得できたことは嬉しかったし、若い人たちに混じって教習員から雑に扱われたのは自らを省みる良い機会になりました。何となく、年を取って自分が偉くなっているという傲慢な思いがあったのは事実だったし。
卒業後の手続きは、教習所に配られた紙を熟読すると、運転免許試験場に行って本番の学科試験に合格する必要があるということだったので、脳みそが衰えないうちに、すぐに受けにいくことにしました。
運転免許試験場というと、横暴な警察官が、これまた上から目線で、非効率的な事務運営をしているのだろうと思い込んでいましたが、実態は違いました。学科試験を受けるための手続きも凄く分かりやすくてシステム化されていて、試験場の職員の人たちも基本的に親切でした。
日本の公的機関の仕事の仕方は、確定申告も改善されたし、役所での各種書類の発行も凄く簡単になりました。人手不足への対応もあるでしょうが、行政機関の生産性は確実に上がっていると思いました。
締め
以上が、私の運転免許取得までの経緯です。
一見難しそうな運転免許を、この年になって時間は掛かったけど取得できたのは、凄く自信に繋がりました。身分証明書としてはパスポートやマイナンバーカードで十分であるものの、いざとなれば車が運転できるというのは"大人"な感じがします。
また、普通自動車の免許を取得すると、仕事に使えるという観点では、タクシー運転手になるための二種免許や中型・大型免許も次のステップとして見えてきます。さすがに、私が今から重機を扱うことは厳しいでしょうけどね。
そんなこんなで、大人の学び直しとしての運転免許取得というのはアリだと思うので、免許を持っていない人はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。