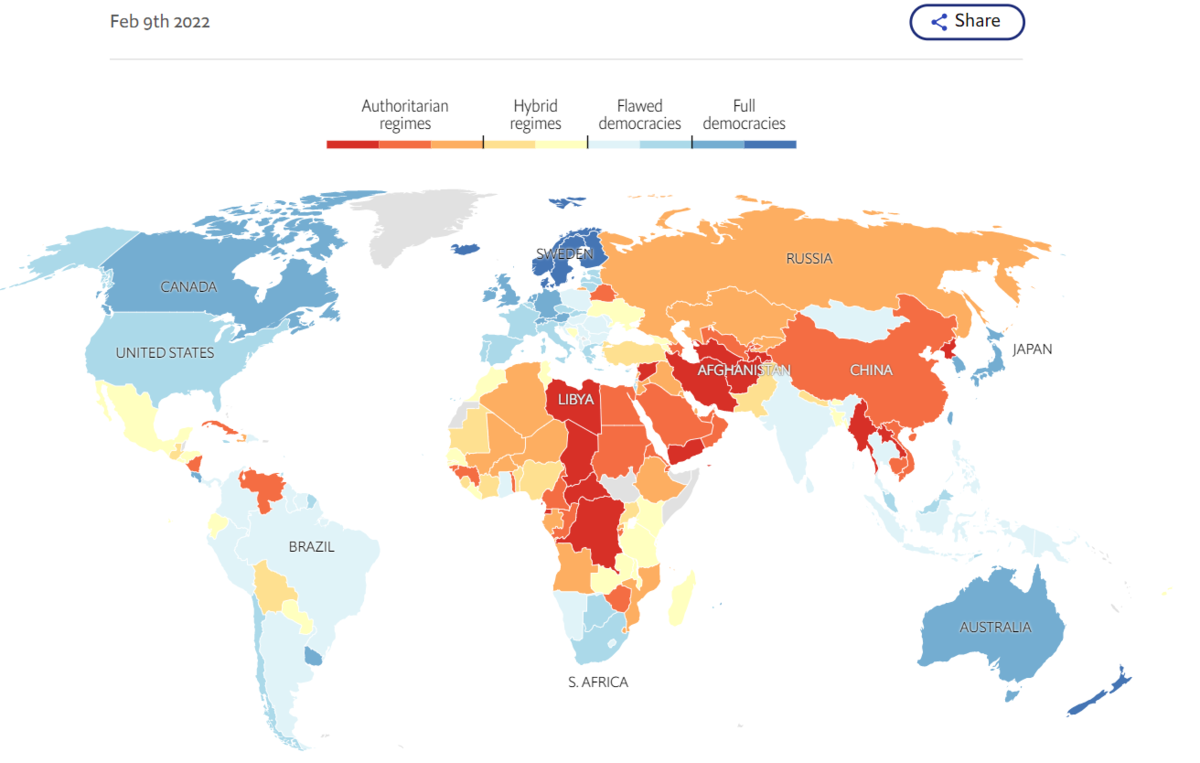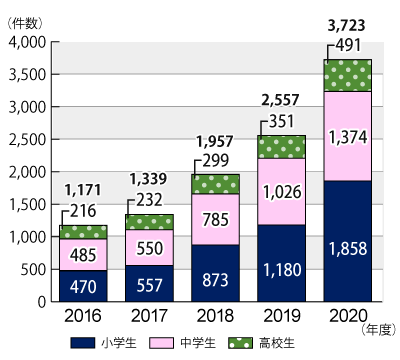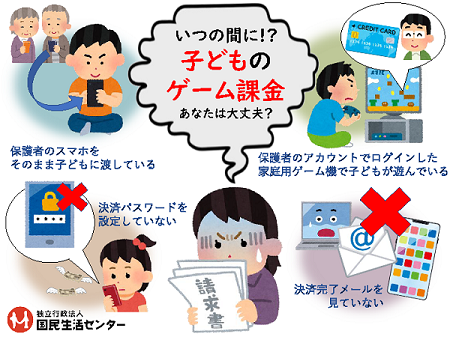今日は一人小町(一人で発言小町みたいな回答をするもの。基本要望に応じた反応をする)です。人間関係のモヤモヤ。

Q. トラブルメーカーで縁を切ったはずの"知人"が私のSNSを監視していた! なぜ!? お祓いをお願いしたい
※太字はtopisyuによるもの
斗比主閲子様
初めまして、昔からブログを拝読しているいち読者です。普段は教育関連の記事を好んで拝読しているのですが、今回はお恥ずかしながら人間関係についてアドバイスをいただきたくメールさせていただきました。
数年前に疎遠にした人がいます。相手(Aとします)は20年来の知人です。学生時代も特に親しくなかった人です。
Aは対人トラブルが絶えない人で、20代の頃だれかと喧嘩した直後に私に連絡がきて再会しました。交流するようになってひと月も経たない内に、他県から私が住む県に引っ越してきて(しかも隣駅)たまに会う関係になりました。これだけの関係でAから親友と呼ばれ、認識の違いに漠然とした怖さは感じておりました。
数年後、とある出来事でAの機嫌を損ね、数日後別件で私の揚げ足を取るようなLINEが送られてきました。
プライドの高いAは地雷を踏まれることに過敏で、踏まれると激昂し問題をすり替えてでも相手を言い負かさないと気が済まない性分でした。(別の人ともこの性分でドロ沼のトラブルになっています/本人は自サバ、いつも冷静なつもりのようでした)
この時は「一線(本音は50線くらい)引いて付き合っていたのに、短所を引き出してしまった」と落ち込みましたが、再会した時から折を見てAとは疎遠になりたいと思っていたこともあり、咎められたことに関しては謝罪し、今まで世話になったお礼をしてLINEはブロックしました。
彼女はバリキャリ独身、外面が非常に良く、有能との本人談ですが、お酒に酔うと不正・いじめ・差別発言などを武勇伝のように語る人でした。
素面の時は気分屋で、気に入らないことがあるとヒステリックに命令口調で怒鳴りつけるという、学生時代教師やクラスメイトから腫れ物扱いされる原因となった悪癖も直っておらず、お互いの認識の違いもあり、気が長い私も疲れ、限界でした。
疎遠になったこと自体に後悔はありません、憑き物が落ちたようでした。
それ以来Aとは会っておらず平和に生活していたのですが、今年に入り私のSNSを2〜3年前からAに特定されていることが人伝に判明。Aには可能な限り個人情報を与えないようにしていましたし、当時知られていた情報では絶対に発見できないはずでした。
気味が悪いのでブロックすると、ブロックされたことに気づいたAはアカ消し逃亡。転生して別のアカウントからまた監視しているのだと思います、気持ち悪いですがAの自由なので好きにすればいいと思っています。
思い返せば同僚や就活生のプライベートアカウントを採用担当でもないのにどこからともなく特定してきたり、親しい友人のTwitterを見せながら馬鹿にし酒の肴にする人でしたので、恐らくそのような使われ方をしているのだと思います。
しかし、どうでもいい人のアカウントを労力をかけて探し出すことに何の得があるのでしょうか。
性格悪いことをしているという自覚はあるようでしたし、どんなに待ってもAの賞賛など絶対に書かれるはずもなく、Aが幸せになれる情報はない=嫌いな人のSNSを覗き見ることは自らストレスを溜める行動だと思うのですが…。
こちらは後ろめたいことは何もないので、これまで通りSNSは継続するつもりですが(悪手でしょうか?)、完全に消えたと思っていた相手が突然現れ、なんとも気味が悪いです。
自分ではAのカタチ、全体像…とでも言うのでしょうか、を言語で上手く捉えることができません。関わりたくない、思い出したくもない人という理由もありますが、Aに怒鳴られたことでAのことを考える時思考が停止します。
またAの人との距離の詰め方が急すぎる一面、恐らく両親のどちらかが時や場所を問わず怒鳴る人だったんだろうと推察されますが、生育環境や教育面で斗比主様が思うことがありましたらお聞きしたいです。
再び現れたAを祓いに祓って祓いまくり、この事態を忘れて気持ちよく日常に戻れるようアドバイスいただきたいです。
もし宜しければご回答いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
一読者より
A. はい、お祓いします。可哀想な人ですね
メールありがとうございます!
忘れていたはずの厄介な人とのトラウマ体験を、その人がSNSストーキングしていることが分かって思い出してしまい、言語化等々で消化吸収したいというモヤモヤですね。
Aさんがどういう行動原理でSNSストーキングをしているかを言語化するのがモヤモヤを解消する手立てになると思われているということで、
しかし、どうでもいい人のアカウントを労力をかけて探し出すことに何の得があるのでしょうか。
これを最初にお答えすると、要はAさんは読者さんのことをまだ諦めきれないということでしょうね。
冒頭に書かれている通り、
Aは対人トラブルが絶えない人で、20代の頃だれかと喧嘩した直後に私に連絡がきて再会しました。交流するようになってひと月も経たない内に、他県から私が住む県に引っ越してきて(しかも隣駅)たまに会う関係になりました。これだけの関係でAから親友と呼ばれ、認識の違いに漠然とした怖さは感じておりました。
Aさんの周囲にはもう友人らしい友人はいないはずで、ちょっとした関係でも築いてくれた読者さんはまさに"親友"だったわけですから。好きの反対は嫌いではなく無関心なんですよね。関係が絶たれた後もずっと相手を嫌い続けるというのは、相手に興味があるからで。
だから、ブロックを止めて、「あの時は私が悪かった。もう一度仲良くしようか」と伝えたら、手のひらを反して、すり寄ってくるはずです。
幸いにも物理的に危険な行為をする人でないというのは、
思い返せば同僚や就活生のプライベートアカウントを採用担当でもないのにどこからともなく特定してきたり、親しい友人のTwitterを見せながら馬鹿にし酒の肴にする人でしたので、恐らくそのような使われ方をしているのだと思います。
という風に酒の肴が限界のようですから、読者さんがSNSを止める必要はなさそうです。
続いて、
自分ではAのカタチ、全体像…とでも言うのでしょうか、を言語で上手く捉えることができません。関わりたくない、思い出したくもない人という理由もありますが、Aに怒鳴られたことでAのことを考える時思考が停止します。
またAの人との距離の詰め方が急すぎる一面、恐らく両親のどちらかが時や場所を問わず怒鳴る人だったんだろうと推察されますが、生育環境や教育面で斗比主様が思うことがありましたらお聞きしたいです。
こちらは、読者さんお推測の通りじゃないでしょうか。あんまり言いたくはないですが、育ってきた環境で無償の愛を受ける機会が乏しかったんでしょうね。
ただ、環境が悪かったとしても成人してからの人生はその人自身のものですし、何度も改善する機会(知人・友人からのフェードアウト)はあったわけですから、今から育ってきた環境を言い訳にすることはできません。
可哀想な人ではあるものの、ここまで失敗体験を積み上げてきてしまうと、自身に問題があることを自覚するのは相当に困難なはず。ましてや他人が何か介入してどうこうできるものではありません。
それにしても、誰かに怒鳴られた経験というのはなかなか癒されないですよね。本当にご苦労様でした。
以上、お祓い完了しましたので、今後は彼女の存在は忘れて、心穏やかにお過ごしくださいませ。
これを読まれたみなさんも、どうぞetsuko.topisyu@gmail.com まで、ブログにそのまま掲載してもよい、ほっこりエピソードをご気軽に送ってください。私が一言コメントを付けてブログに掲載します。
なお、投稿にフェイクを入れるのは確認で時間がかかるので、ご自身でするか、私に全面的にお任せする形でお願いします。また、どんな方向でコメントをしてほしいかも書いてくれたら、期待に応えるようにします。罵ってほしい、褒め称えてほしい、傾聴してほしい、何でもOKです。
X(旧Twitter)もやっているので、
ブログの関連Tweetとかを読みたければフォローしてやってください。